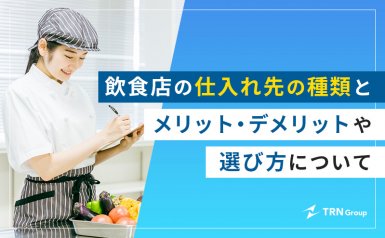食品ロスの原因や対策とは?飲食店のできる取り組みや利益改善につながる解決策をご紹介
- 公開日:
- 更新日:

飲食店の営業でどうしても発生してしまう食品ロス。利益を確保するためにも、食材は廃棄することなく大事に取り扱いたいものです。本来食べられるはずの食品が廃棄されることで、経営上の損失に直結するだけでなく、社会的な課題にもつながります。本記事では飲食店の食品ロスの原因と、その対策について解説していきます。

目次
日本における食品ロスの実態

「食品ロス」とは、本来食べられるはずなのに捨てられてしまう食品のことを指します。食べ残しや腐らせて食べられなくなった料理・食材などがこれにあたります。
農林水産省によると、日本の食品廃棄物等は年間2,550万トンにも上るとされています。そのうち、「食品ロス」の量は612万トン(※1)です。612万トンというと、数字が大きすぎてイメージしづらいかもしれませんが、日本人1人当たり年間約48キロの食品を廃棄している計算になります。
この食品ロスの量は、大まかに「家庭系」と「事業系」に分けることができます。その内訳をさらに細かく見ていくと、事業系の中にある外食産業では年間127万トンの食品ロスが発生しています。この数字は事業系食品ロスの中でトップであり、そもそも飲食業界は食品ロスが出やすい業界ということがこのデータからわかります。
食品ロスは飲食店経営における課題であり、日本を含む世界的な課題でもあります。健全な経営・社会的貢献のためにも、お店の現状を見直して食品ロスを減らす取り組みをしていきたいところです。
(※1)出典:環境省「我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの発生量の推計値(平成29年度)の公表について」
飲食店における食品ロスの原因と対策

飲食店は食品ロスが多い業態であることがわかりました。では、飲食店の食品ロスの原因はいったい何にあるのでしょうか? ここでは飲食店の食品ロスの原因について探っていきましょう。
廃棄ロスの発生
廃棄ロスとは、賞味期限切れや腐敗した食材を廃棄することを指します。主な原因としては、以下の点が挙げられます。
- 仕入れや在庫管理の不備:適切な量の仕入れや在庫管理ができていない場合、余剰食材が発生し、結果的に廃棄することになります。
- 厳格な衛生管理:飲食店では食中毒を防ぐために、食材や料理の衛生チェックが一般家庭よりも厳しくなります。そのため、廃棄量が増える傾向にあります。
対策:食材の使用期限を管理する仕組みを整えることや、過剰な仕入れを防ぐための発注方法を見直すことが重要です。
お客様の食べ残し
食品ロスの中でもお客様の食べ残しは大きな割合を占めており、外食産業全体の約50%がこの要因で発生していると言われています。
- 提供量の過多:サービスの一環としてボリュームを重視するあまり、食べきれない量の料理を提供することがあります。
- お客様の食事スタイル:現代では「少食」「健康志向」のお客様も増えているため、必要以上の量を提供すると食べ残しが増える可能性があります。
対策:
- 料理の分量見直し:提供する料理の適正な量を再考し、食べ残しを減らす工夫をする。
- ハーフサイズや小盛りの導入:お客様に量を選んでもらえるオプションを追加することで、満足度を保ちながらロスを削減できます。
オーダーミス・調理ミス
オーダーミスや調理ミスも食品ロスの一因です。具体的には、以下の状況が考えられます。
- 注文内容の聞き間違い
- 調理中の失敗や確認不足
- サービスの混雑時における対応ミス
対策:
- オーダーシステムの見直し:デジタル端末やオーダー管理ツールを導入し、注文ミスを防ぐ。
- スタッフ教育の徹底:調理手順の共有や確認フローを整備し、ミスを減らす体制を構築する。
食品ロスの削減は利益改善に直結する
食品ロスは飲食店にとって、単なる損失ではなく「利益を失う要因」でもあります。
例えば、飲食店の平均原価率は約30%とされていますが、実際には食品ロスが発生することで原価率はさらに高くなる傾向にあります。具体的には、約3〜5%の食材が廃棄されているとも言われています。
食品ロス削減のメリット
- 原価率の低減:ロスを減らせば、その分原価率が下がり、利益が向上します。
- 経営の安定化:無駄なコストを削減することで、店舗経営の安定につながります。
- 社会的価値の向上:食品ロス削減への取り組みは、環境問題に貢献するだけでなく、顧客からの信頼や評価向上にも寄与します。
このように、食品ロスの割合を減らすことは利益アップに直結します。そのため、食品ロスの発生を防ぐことは、飲食店の経営を安定させる大きな取り組みだと言えるでしょう。
飲食店の売上をアップさせるための具体的な施策を紹介していますので、こちらも参考にしてみてください。
飲食店の食品ロスを減らす方法は?
飲食店の食品ロスを減らすには、工夫や努力が必要です。ここからは、ロスの発生を防ぐための方法についてご紹介します。
1、食品ロス率を計算する
食品ロスを減らすための第1歩として、ロス率を計算することをおすすめします。ロス率とは、売上に対する食品ロスの割合のことです。食品ロス率をしっかりと管理することで、自分の店でどれだけ食品ロスが起こっているかを把握することができます。
食品ロス率の求め方は以下の通りです。
食品ロス率の計算方法
- 食品ロス金額=廃棄した商品の販売価格 × 廃棄個数
- 食品ロス率(%)=(食品ロス金額÷売上高)×100
(例)原価500円の魚を10匹仕入れ、8匹は売価1,200円で販売に成功、2匹は腐らせて廃棄した場合
- 売上高:8匹×1,200円=9,600円
- 食品ロス金額:2匹×1,200円=2,400円
- 食品ロス率:(2,400円÷9,600円)×100=25%
一般的なロス率は3~5%と言われているため、上記の例で出たロス率は高めということがわかります。
このロス率は原価や仕入れをコントロールするための指標となります。そのため、ロスした食品や料理について管理する「ロスノート」の作成がおすすめです。自分の店舗でどれだけのロスが生じているかを知ると、何に取り組むべきかが見えてくるはずです。
2、適正な発注・在庫管理を行う
発注や在庫管理のミスは食品ロスの大きな原因です。必要な食材量を把握し、適切に管理することでロスを防げます。具体的な方法は以下のとおりです。
- POSレジを活用:売上データから曜日や天候、イベント時の需要を予測し、発注量を調整する。
- 先入れ先出しの徹底:古い食材から使うことで、在庫の鮮度を保ちます。
- 保管環境の最適化:冷蔵庫を清潔に保ち、食材が傷まないよう管理を徹底する。
仕入れに関する詳しいポイントは、こちらの記事でも解説しています。ぜひご覧ください。
3、メニュー・レシピを見直す
お客様の食べ残しが多かったり、調理ミスが頻発するようであれば、料理メニューやレシピの改善を考えるべきです。お客様の食べ残しが多いメニューは、提供する料理の分量が適していない可能性があります。その場合は、小盛りメニューの導入や分量が選べるようなメニューづくりを検討してみましょう。
調理ミスがよくあるメニューについては、レシピの見直しが必要です。難しい調理工程があるのならそれを簡略化する、詳細にレシピを設定する、熟練者だけが担当するなどの工夫が考えられます。
さらに、特定の料理に特化した専門店のような業態は食品ロスが少ないとされています。その理由はメニューのカテゴリが絞られているため、ひとつの原材料を多くのメニューで使っている点にあります。原材料ベースで料理レシピを考え、ロスの少ないメニューづくりを目指すのもひとつの手です。注文が少ないメニューは定期的に見直し、不必要なものは思い切ってはカットしていきましょう。
4、オーダーミスを防ぐルールを徹底する
オーダーミスは食品ロスを生むだけでなく、お客様の満足度低下にもつながってしまいます。
具体的なオーダーミス対策3選
- 復唱確認の徹底:注文内容をお客様に確認する習慣をつける。
- セルフオーダーシステムの導入:タッチパネルなどの電子メニューで注文ミスを防ぐ。
- メニューの工夫:わかりやすい料理名や説明を記載し、お客様の誤解を防ぐ。
5、お持ち帰りの対応
お客様が食べ切れなかった場合の対策として、お持ち帰りをしてもらうという方法があります。自分の食べ残しをもったいないと考え、家に持ち帰りたいと考えているお客様は一定数いらっしゃいます。
しかし、一度手をつけた料理を持ち帰ることは、衛生面での注意が必要となります。刺身などの生食のお持ち帰りは断る、基本はお客様の自己責任ということを説明するなど、ルールづくりを徹底しましょう。
6、フードシェアリングサービスの活用
なかなか食品ロスを減らせない店舗は、フードシェアリングサービスを利用してみてはいかがでしょうか? フードシェアリングとは、廃棄する予定の食材や料理を格安で販売するサービスです。食品ロスが世界的な問題として関心が高まりつつある中、フードシェアリングは食品ロスを減らす取り組みとして注目を集めています。
フードシェアリングのメリット
フードシェアリングサービスを使うことのメリットは食品ロスをなくすことだけでなく、売上の確保や店舗のブランディング効果などにもあります。専用サイトに登録し、スマートフォンやPCなどから簡単に出品することができる手軽さも、フードシェアリングサービスの魅力です。
飲食店の食品ロス削減を成功させるために
食品ロスは、飲食店経営の課題であると同時に、社会全体が取り組むべき重要なテーマです。食品ロス率の計算や在庫管理、メニュー改善、オーダーミス対策を徹底することで、無駄を減らしつつ利益向上と社会貢献の両立を目指しましょう。
食品ロス削減への取り組みは、経営の安定化だけでなく、持続可能な社会の実現にも寄与します。積極的にチャレンジしていきましょう。